チェルノブイリツアー、いざ出発



ついにチェルノブイリツアー当日がやってきた。興奮しすぎて早朝に目が覚め、少し早めに待ち合わせの独立広場へ。
朝のやわらかい日差しを浴びながらしばらく待っていると、ツアーに参加するらしき人たちがちらほら集合。やがてツアー会社のスタッフがやってきて、パスポートチェックを始めた。
参加者は十数人で、ほとんどが欧米から来た人たち。アジア系は香港出身の2人と僕だけだった。
2台のバンに分かれて乗り込むと、車内のテレビからチェルノブイリのドキュメンタリーが流れはじめる。ガイドが注意事項を説明し、事前に申し込んでおいたガイガーカウンターが手渡された。
周りはこの黄色の測定器に興味津々で、我も我もとレンタルを申し出た。ちょっとだけ優越感が湧いて、顔がにやけてしまう。
チェルノブイリへの玄関口




バスに揺られて1時間ほど経った頃、急に停車して制服姿の軍人が車内に乗り込んできた。お約束のパスポートチェックが始まり、全員おとなしく待機モード。いよいよここから立入禁止エリアに入るらしい。
無事にチェックを終えて外に出ると、だだっ広い道路の真ん中に堂々と検問所が立っていた。ここは原発からおよそ30kmの Dityatky という町。
軍人や軍施設を撮影しないよう厳重に注意されたので、代わりに手前に置かれた戦車とギフトショップを撮影。歴史に残る大惨事の地にもかかわらず、メッセージ性ゼロの土産グッズがずらりと並ぶ姿はある意味で熱い。
極めつけはチェルノブイリブランドのアイスクリーム。買いはしなかったが、たぶん普通に美味しいのだろう。
チェルノブイリの町に到着


検問所を抜けてしばらく走ると、原発から約20kmの地点にあるチェルノブイリの町の入口に到着。そこにはソ連時代を思わせる古びた看板がぽつんと立っていた。
今では世界的に不幸な場所として知られてしまったが、きっと昔はウクライナにあるのどかな田舎町のひとつだったのだろう。
ちなみに試しにガイガーカウンターを起動して放射線量を計測してみたら、0.14μSv。ガイドいわく、0.5μSvまでは正常値らしいので、とりあえず一安心。
止まった時間と不気味なラッパ





次にバスが停まったのは、レーニン像 の前。ソ連の支配、人工的大飢饉、そして世界最大級の原発事故…そんな歴史を背負った場所に彼の像が今も立っているのは、もう痛烈な皮肉としか言いようがない。雑草に埋もれながらも風化しきらずに残る姿は、ここだけ時間が止まっているかのようだった。
少し先には、ラッパを吹く不気味な天使の彫刻が出現。聖書に「天使がラッパを吹くと、ニガヨモギという名の星が落ちて水が苦くなり、多くの人が死んだ」という話があるらしく、それを原発事故に重ねているらしい。つまり、これは宿命だったと言いたいのだろうか…。
その天使の彫刻の向かいには、ずらりと墓標が並ぶ道が続いていた。殉職者を祀っているのかと思いきや、全部が 原発事故で立ち入り禁止になった町の名前だった という衝撃。この数の多さが、放射能という悪魔のスケールを無言で物語っていた。
世界を救った人々の記念碑


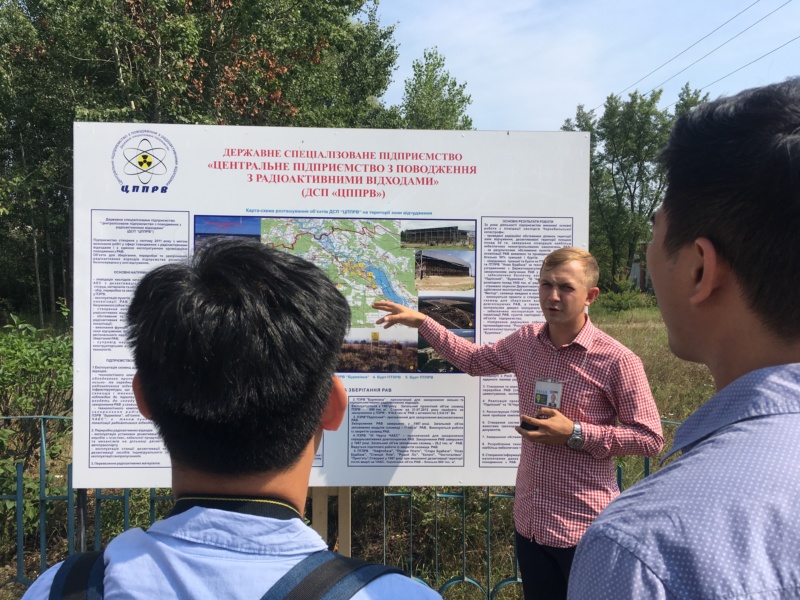
チェルノブイリの町には、他にもいくつか記念碑や展示が点在している。中でもひときわ胸に残ったのが Monument Of Those Who Saved The World。事故直後に消火活動にあたって命を落とした人たちを追悼する碑だ。
彼らはきっと、何も知らされないまま死地に向かったのだろう。何故なら、過去にも現在にも、あの放射線を完全に防ぐ防護服は存在しないのだから。(しかも、当時のソ連はスウェーデン政府から指摘されるまで原発事故そのものをひた隠しにしていた)
チェルノブイリでランチタイム


お昼はチェルノブイリの町にあるログハウス風のレストランでランチ。てっきり軍の施設で無機質な給食でも食べるのかと思っていたので、意外と洒落た建物にびっくりした。
放射能を象徴するこの土地で、普通にパンとスープと肉を安心して食べられるというのは、なんとも不思議な気分。
もちろん放射線レベルもきっちり正常値で問題なし。同席したツアー仲間と軽く会話もできて、意外と和やかで有意義な時間だった。
(続く)